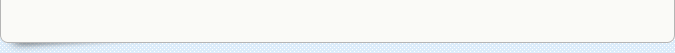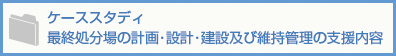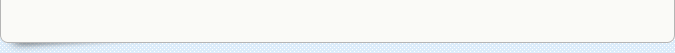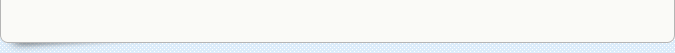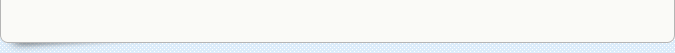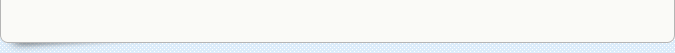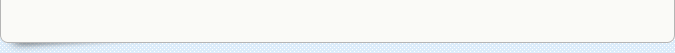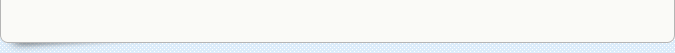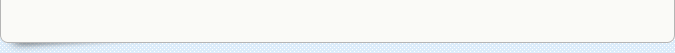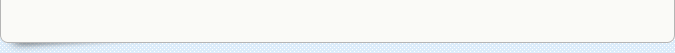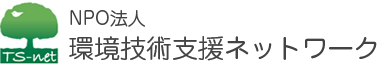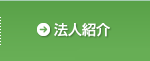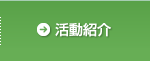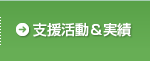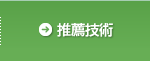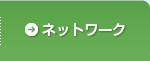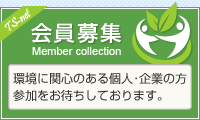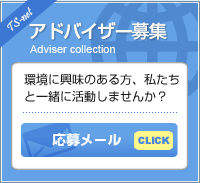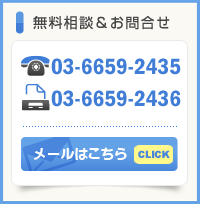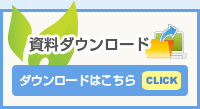環境技術支援
1.自治体、団体、民間企業への技術支援。
2.土壌、低質、焼却灰、水、大気のダイオキシン類、重金属類等有害物質の浄化支援。
3.中間処理場、最終処分場等の計画、設計、施工監理支援。
4.焼却場の解体工事積算及び安全解体、ダイオキシン等の現地無害化。

有料となった時の費用は高いのでは?
営利企業と違いNPO法人(非営利活動法人)ですので、NPO法人の運営・活動に必要な範囲での費用です。事前協議にもよりますが基本的には成功報酬です。
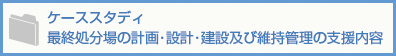
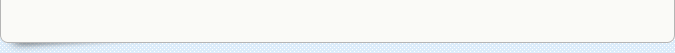
コンストラクション・マネジメント(CM)方式の啓発
1.発注者(自治体・団体・民間企業)の立場に立った技術支援。
2.第三者機関(非営利活動法人)としての中立・公平性を生かした支援。
3.コンストラクション・マネージャー(CMR)を独自に育成し認定する。
※コンストラクション・マネジメント(CM)方式は平成14年2月に国土交通省が策定した制度です。
※発注者側に立って、計画・設計・発注・施工管理段階での補助・支援を行うことで、発注者側の技術者不足・経験不足を補う制度です。
>国土交通省CM方式活用ガイドライン詳細参照

CM方式の今後の見通しは?
近年の入札方式等の見直しと不法投棄の対策や処分場の建設、焼却場の解体等何十年に一度の工事等には技術者不足・経験者不足が目立ち、コンストラクション・マネージャーの必要性は急速に増すと思われます。

CM方式におけるNPOの位置づけは?
一部専門業者(コンサルタント会社)が行なっておりますが、経費の面からもコンプライアンス上からも非営利活動法人が第三者機関として活動することが望ましいと考えます。

CMの範囲は?
国土交通省のCM方式活用ガイドラインの①~④の範囲でアットリスク型CMは行なっておりません。
① 設計・発注アドバイス
② コストマネジメントアドバイス
③ 施工マネジメント
④ 総合マネジメント
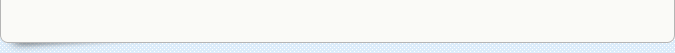
安全管理・コンプライアンス・LCA/LCC評価支援
1.環境保全事業等を定質・定量で評価。
2.各種浄化工事の計画・設計・管理・施工を化学的に管理・評価。
3.実施者だけの一元管理でなく、第三者の立場からのダブル管理が安全・安心につながります。

安全管理・コンプライアンスとは具体的には?
発注者が問題が発生してから第三者機関を設置することがありますが、問題が発生する前に計画段階から第三者機関とダブルチェックをしながら進めることが安全・安心につながると思います。

LCA・LCCでの総合評価の目的は?
CO2排出量やエネルギー消費による環境負荷を数値で評価したり、コスト数値とのマトリックスで評価することで、誰にでも分かり易く透明性を確保することが出来ます。
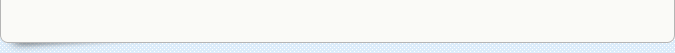
事業化支援
1.ベンチャー(個人)開発の重金属類・塩類無害化システム事業化支援。
2.焼却場から排出される主灰・飛灰の重金属類・塩類を無害化。
3.中小企業、ベンチャー企業の新規事業化支援。
4.研究開発成果のビジネス支援。
5.研究成果をビジネスに、また環境保全に役立つように支援します。

研究開発成果のビジネス支援をもう少し詳しく?
産学官を初め多くの研究が行なわれており、しかもその研究が税金で補助されていることもあります。また、その研究が世のために貢献しているか疑問です。研究が研究だけに終わらず成果が発揮できる支援をしたいと思います。

事業化への支援方法は?
研究開発の成果を広く告知し、技術・企画・営業アドバイザーでプロジェクトを構成し、他の研究成果とのコラボレーションも視野に入れた支援をします。
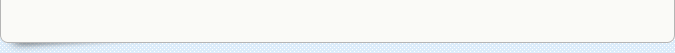
産学官連携及び研究開発支援
1.産学官のマッチングと研究開発支援
2.協働研究のコーディネート、事務局、企画、文献調査等のスタッフ支援

スタッフ支援をもう少し詳しく知りたい。
研究テーマにあった産学官との連携をサポートします。また、協働研究の運営や事務処理及び文献調査・特許調査は意外と多く、本来の研究の妨げになっていることがありそれらを支援します。

補助金研究支援とか委託研究への支援も?
関係官庁や各自治体から毎年多くの研究開発補助金や委託研究の公募がありますが、採択されることは難しい状況です。このような公募に対し経験豊かな技術アドバイザーにより採択のコツを支援します。
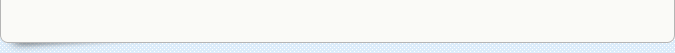
推奨技術の普及支援
1.NPO法人という第三者機関の立場から環境負荷軽減に優れた技術を推奨技術と認定します。
2.認定した技術は広く普及を支援します。

普及に対する費用は高いのでは?
営利企業と違いNPO法人(非営利活動法人)ですので、NPO法人の運営・活動に必要な範囲での費用です。事前協議にもよりますが基本的には成功報酬です。
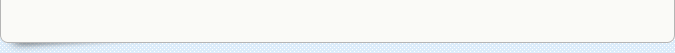
セミナー・見学会の開催
1.NPO法人ならではのセミナーや見学会の開催に勤めます。
2.幅広い情報収集により皆様のお役に立てるよう目指します。

セミナー・見学会の参加費用は?
会員の方は基本的には無料ですが、実費交通費やテキスト代が掛かることもあります。
非会員に方にも出来るだけ実費の負担をお願いしております。
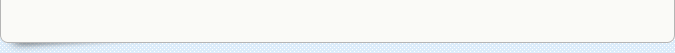
ケーススタディー:最終処分場の計画・設計・建設及び維持管理の支援内容
① 最終処分場残余容量調査業務
平成17年度より最終処分場の残余容量を毎年測定することが法律で義務付けられています。
毎年の測量調査に掛かる費用を軽減するため、私たちは初年度のみ測量し、それ以降は管理者自らの簡易測定により、算出できるシステムを構築いたしました。(特許出願済み)

搬入重量から換算して算出しているので、測量する必要はないのでは?
環境省が示している「残余容量算定マニュアル」において、重量から換算できるのは、海面埋立等の実際測量が不可能なところや、埋立物の体積換算係数が、ほぼ一様であり、実測により定期的に把握されている処分場に限られています。原則は測量等の調査により把握することになっており、私どもが提案する手法は、同マニュアル内で示されている簡易手法に合致したものです。
② 最終処分場浸水出削減化計画、設計
近年の降雨パターンの変化により、浸出水量が計画量を上回り、適切な処理に支障をきたしている事例や、処分場内に内部貯留することで、廃棄物の安定化阻害や、遮水工に対するリスクの増加といった問題が多く発生しています。
私たちは、処分場の現状を調査し、水収支を明確にし、浸出水の削減化計画の立案、設計を行います。
③ 最終処分場健全性検査業務
最終処分場の機能検査を行い、その健全性について評価、改善提言を行う業務です。
最終処分場を長期間使用するなかで、各設備それぞれの機能の低下や、維持管理も含めた、処分場全体としての健全性に対する確認を行うことで、安全性の維持向上を図る、いわば「処分場ドック」です。
④ 最終処分場計画設計業務
これまで建設コンサルタントが行ってきた計画、設計業務に加え、全体のコーディネート、住民の方々への技術的な説明のサポート、関係機関との協議、設計会社への設計指導等の技術支援を行います。
⑤ 最終処分場計画設計安全性評価業務
現在計画されている最終処分場が計画設計の立場から、安全性がどの程度高いものなのか、また、より現実的な安全性向上に関する提案がないのか等を評価することで、より安全性の高い施設の建設に貢献し、住民の方々や関係機関の正しい理解をいただき、施設の設備に貢献することを目的とします。
⑥ 最終処分工場民間検査業務
建設中の処分場について、建設段階で民間検査機関としての段階検査を行い、安全性の確保、向上に貢献します。このNPOによる検査は、住民の方々に対しての安心材料となるものです。
⑦ その他の廃棄物処理施設関連業務
最終処分場に限らず、焼却施設、リサイクル施設等の廃棄物処理施設の建設、維持管理、解体等に関する様々な問題、課題に対して、必要な支援を行うことが可能です。